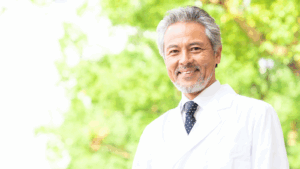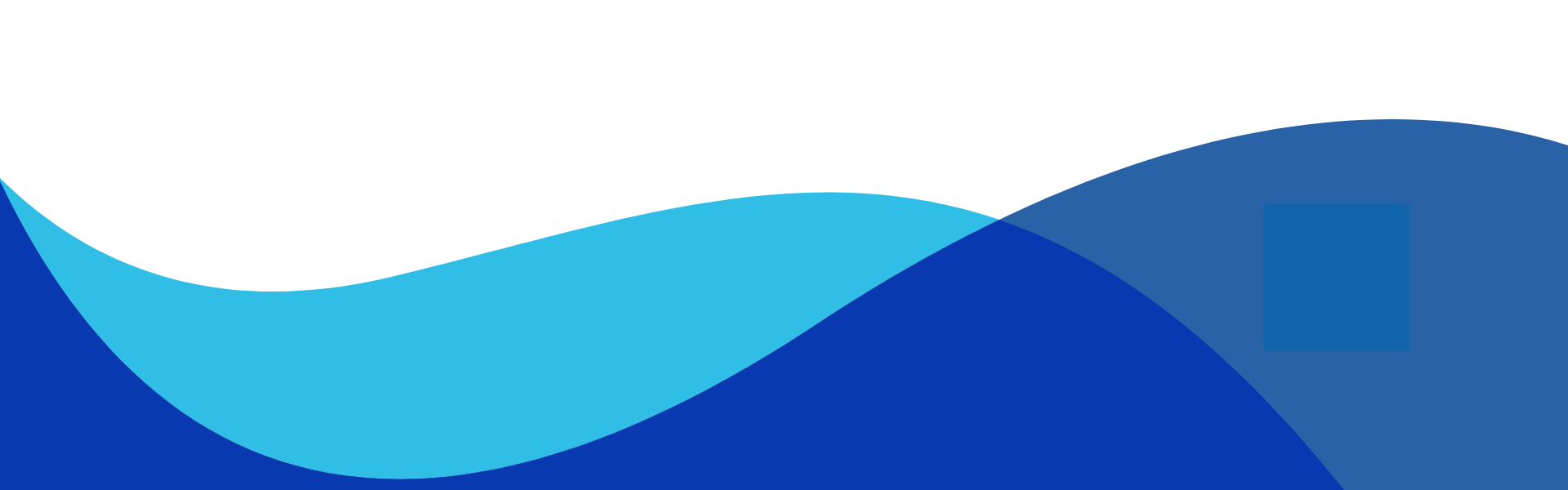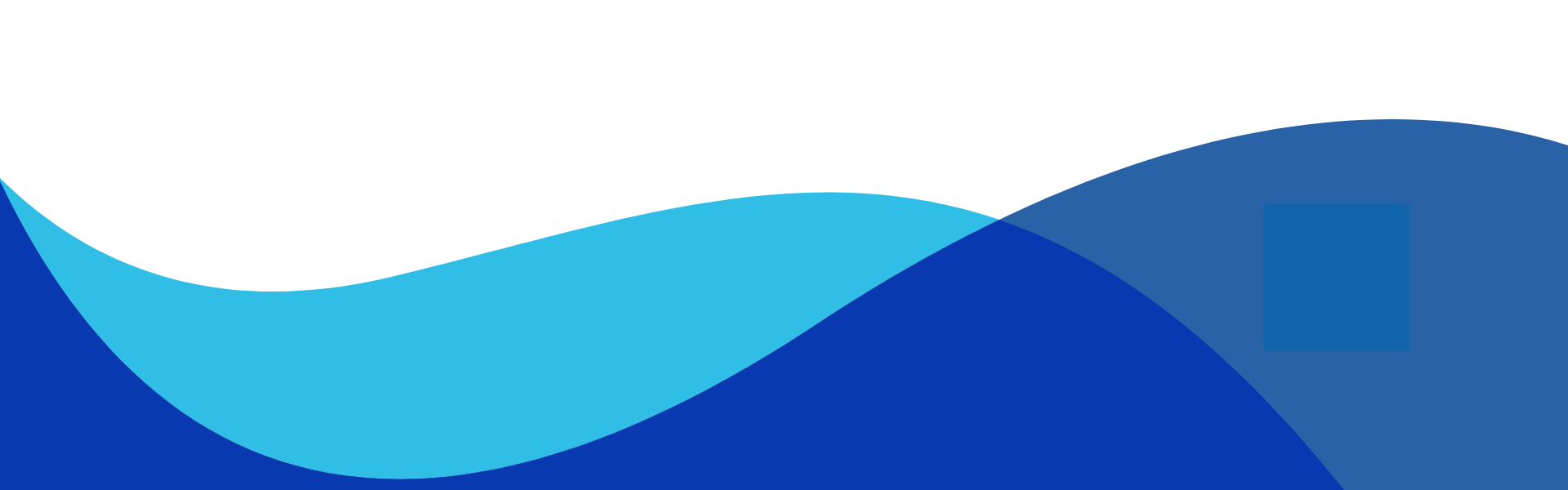分院の分水領

クリニックを運営している先生のなかには、「将来的には分院もしたい」と考えている人もいるかと思われます。以前の記事では、「分院とは何か、そのメリットとデメリット」について解説しましたが、今回は「分院の分水領・分院をするタイミング」について解説していきます。
所得1800万円以上もしくは保険診療報酬5000万円以上
分院を考えるタイミングを計るひとつの目安として、「収入」があります。
この「収入」は、
・個人の所得
・クリニックの売り上げ
の2つに大別されます。
個人の所得で考えた場合は、年収が1800万円以上であることが基準となります。日本は累進課税方式をとっていて、所得が多ければ多いほど税率も大きくなります。年収が195万円以下の場合はわずか5パーセントですが、これは段階的に引き上げられていき、1800万円を超えるとなんと税率は40パーセントにまでなります(※控除額あり)。
しかし医療法人の場合は、大きくても23.2パーセントとなるので、控除額を考慮に入れても、法人化した方が税金が安くなります。
また、クリニックの売り上げから、法人化をするタイミングをはかることもできます。
医療法人の場合は、経費計上において、社会保険診療に関わる費用の計上が認められています。これは、「実際に必要になった金額」ではなく、「概算経費」として計上することが可能になっています。売り上げによっては、実際にかかった経費よりも、500万円以上も多く経費計上をすることができます。
ただこの制度は、保険診療が5000万円以上かつ保険診療+自由診療報酬7000万円以下でなければ利用できません。そのため、これ以上の売り上げを得ているのであれば、医療法人化する方が望ましいといえます。
単純に「売上」だけで見ないことも重要
上記では、「個人としての所得1800万円以上、クリニックの保険診療額5000万円以上(かつ保険診療額+自由診療額=7000万円以上)を、分院のひとつのタイミングとしました。
しかし、分院を現実的なものとして考える場合には、「黒字経営を続けていけるかどうか」も見る必要があります。
たとえば2022年は赤字で、2023年も赤字で、2024年のみ黒字だった……という場合は、まだ分院に踏み切るのは待った方がよいでしょう。クリニックは、開業してから1年程度は赤字であることが多いとされていて、その分の損益を本院で吸収しなければなりません。本院が安定して経営できていない場合、「共倒れ」になる可能性が高いからです。
「何年黒字経営をしていれば、分院を出して良いか」については諸説ありますが、数年程度は待った方がよいでしょう。
人材が確保できている・人材の育成環境を整えられているかどうかも見る

分院は、ただ建物を建てれば終わりというものではありません。クリニックはその特性上、国家資格を有した医師・看護師の確保が必須ですし、受付業務などを担当するスタッフを配置することも求められます。そのため、人材を確保することが必須です。また、雇い入れた人材を育成できる環境も整えておかなければなりません。
分院を展開するタイミングとして、
・本院で、効率的に業務をまわせるオペレーションやマニュアルの整備ができている
・人材を育成するための環境が整っている
・(可能であれば)分院を任せられる医師を育て上げている
というものがあります。
信頼できるスタッフがいればそれが一番良いのですが、そうではない場合でもしっかりした人材育成マニュアル・運営マニュアルが整っていれば、分院を展開しても成功する確率は高くなるといえます。
「分院」は、クリニックにとって非常に大きな分岐点となります。経済的な負担が大きい反面、自院の医療の理想を追求したり、多くの患者様に自院の医療を提供したり、収入アップに繋がったりするものでもあります。
私たちは、「将来的に分院をしたいが、どうすればいいか」「分院をするかどうか迷っている」「分院をしたが、経営が上手くいかない」という先生方の悩みに寄り添います。